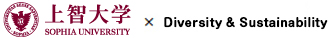お知らせ
ダイバーシティ・ウィーク2024にてヘラルボニー協力企画を開催しました!

多角的アプローチ
2025年1月7日 イベントレポート
2024年11月25日~12月10日に、上智学院ダイバーシティ・サステナビリティ推進室主催のもと、「ソフィア・ダイバーシティ・ウィーク2024」が開催されました。
11月27日には、株式会社ヘラルボニーとダイバーシティ・サステナビリティ推進室の協力企画として、体験型ワークショップが行われました。これは、株式会社ヘラルボニーウェルフェア事業部のコンテンツクリエイターである菊永ふみ氏を講師として迎えた、マイノリティを疑似的に体験しながらチームでミッションクリアを目指すボードゲーム型ワークショップです。
本記事では、ワークショップに参加した学生職員のレポートを紹介します。
今回私は、「異彩を、放て。」をミッションに掲げるヘラルボニー協力企画へ参加してきました。当日は、学部や学年の垣根を超えた30名程度の学生が参加し、大いに盛り上がりました。
開始早々に私が驚いたのは、講師として来てくださった菊永ふみさんがろう者である、ということ。ワークショップは、手話通訳の方や参加者が話す言葉をそのまま即座にスクリーンに映し出す音声文字変換機能を使用して行われました。

ワークショップの中心となるゲームの内容は、見えにくい役や発言に制限がある役をチーム内で振り分け、役になりきりながら時間内に協力して謎解きを行う、というものでした。私は、ゲームの前半では発言に制限がある役、後半では車いすの役として床に座布団を敷いて車いすユーザーの方の目線の高さを体験しました。

私たちの班では、視野狭窄メガネを着用した「見えにくい役」の人が、他のメンバーから得たさまざまな視覚情報を整理し、それをチーム全体に共有してくれたことで、多くの謎を解決することができました。こうした、それぞれの役割を生かした視点を通じて、ヘラルボニーの思想である「“普通”じゃない、ということ。それは同時に、可能性だと思う。」を肌で感じることができました。

私は、発言に制限がある役を担当した際、時間が限られた謎解きの中で、うまく話せない自分に時間を割かせてしまうことを申し訳なく感じたと同時に、この役割にどう対応すれば良いか分からない周囲の戸惑いも伝わってきて、ますます発言がしづらくなりました。私は、このときの私と同じような状況を抱える方々に、もしかしたら日常生活で出会っていたかもしれません。しかし、私はそのような方々の存在に気づき、行動を起こすことができていただろうか、と今回のワークショップを通じて考えさせられました。そして、自分の「当たり前」を基準にした無意識の圧力を誰かにかけていた可能性に気づきました。
記事冒頭で、菊永さんがろう者であることに驚いた、と書きましたが、これはきっと「耳が聞こえない方はどのように講演をするんだろう」という受動的な不安から生まれた気持ちだったのだと思います。今回のワークショップを通して、社会に属するすべての人がダイバーシティを尊重した社会を創る当事者であることを自覚し互いに助け合う、積極的な行動がとても大切なことを学びました。この学びを忘れずに、受動的な不安を積極的な思いやりの行動に繋げられるような活動を学生職員として行っていきたいと思います。
この場をお借りして、このような貴重な機会を提供してくださった株式会社ヘラルボニーの皆様に感謝いたします。
(学生職員:大田原)